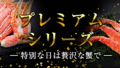※本記事にはプロモーションが含まれています。
発表会や大会は「特別な一日」だからこそ悩みも多い
バレエやピアノ、ダンス、スイミング、空手など、多くの習い事には発表会や大会があります。日頃の練習の成果を発揮する大切な場であり、子どもの成長を感じられる機会でもあります。一方で、衣装の準備や送り迎え、費用やスケジュールの調整など、親にとっては負担を感じやすいイベントでもあります。
また、子ども自身も「うまくできるかな」「失敗したらどうしよう」と不安を抱えることがあります。発表会や大会がきっかけで、習い事自体が好きになったり、逆に苦手になってしまったりすることもあり、その関わり方には慎重さが求められます。
この記事では、発表会・大会がある習い事のメリットと、親としてどのように関われば子どもにとって良い経験になるのかを考えていきます。

結果以上に「過程」を見守る姿勢が大切
発表会や大会は、どうしても「成功したかどうか」「賞が取れたかどうか」に目が向きがちです。しかし、子どもにとって本当に大切なのは、本番を迎えるまでの練習の過程や、不安を抱えながらもステージに立った経験そのものです。
親が結果だけに注目してしまうと、「失敗したら怒られるかも」「いい結果じゃないと意味がない」と感じてしまう子どももいます。そうなると、発表会や大会が楽しみなイベントではなく、プレッシャーの源になってしまいかねません。
まずは、「ここまでよく頑張ってきたね」と、本番を迎えるまでの努力に目を向けることが、子どもにとって大きな安心材料になります。
発表会・大会がある習い事のメリット
大変さもある一方で、発表会や大会にはその場でしか得られないメリットがたくさんあります。
① 自分の成長を実感できる
普段のレッスンでは、「少しずつできることが増えている」ことに本人が気づきにくい場合があります。発表会や大会のような本番の場は、これまで練習してきたことが一つの形となって現れる貴重な機会です。
緊張しながらも最後までやり遂げた経験は、「自分はここまでできるようになったんだ」という自信につながります。たとえ小さなつまずきがあっても、それを乗り越えようとした過程に大きな意味があります。
「去年より堂々としていたね」「前よりも動きが大きくなったね」など、具体的に変化を伝えてあげると、子どもも自分の成長を実感しやすくなります。
② 目標に向かって努力する経験ができる
発表会や大会の予定が決まると、「それに向けて頑張る」という明確な目標が生まれます。日々の練習に意味を見いだしやすくなり、「ちょっと疲れていても、もう少しだけやってみよう」と気持ちを切り替えるきっかけにもなります。
努力がすぐに結果に結びつかないこともありますが、「頑張ったからこそ本番に立てた」という経験は、将来ほかの場面でも役立つ土台となります。
途中で弱音を吐きながらも、少しずつ前に進んだ経験自体が、子どもの中に大きな価値として残っていきます。

③ 仲間との一体感や協力の大切さを知る
グループでのダンスや合奏、チームスポーツの大会などでは、仲間と一緒に一つの目標を目指す体験ができます。「自分一人だけ頑張ればいい」というわけではなく、お互いに声をかけ合い、励まし合う時間が生まれます。
特に、本番直前の緊張感や終わったあとの安堵感を仲間と共有することは、子ども同士の絆を深めるきっかけにもなります。友達の頑張りを目の当たりにすることも、子どもにとって刺激になるでしょう。
こうした経験は、学校生活や将来のチームワークにも活かされていくことが期待されます。

親が気をつけたい関わり方のポイント
発表会や大会を良い経験にするためには、親の関わり方も重要です。ここでは、意識しておきたいポイントをいくつか紹介します。
① 結果より「挑戦したこと」を言葉にして認める
本番が終わった直後に、「どうしてそこを間違えたの?」「もっとできたはずなのに」といった言葉をかけられると、子どもは自分の頑張りを否定されたように感じてしまうことがあります。
まずは、「最後までやりきってすごかったね」「ステージに立つだけでも勇気がいったよね」と、挑戦した事実そのものを認める言葉をかけてあげることが大切です。子ども自身は、うまくいかなかった部分をすでに一番よく分かっていることも多いです。
落ち着いてから振り返りたい場合も、「次はどんなふうにやってみたい?」と、前向きな視点で話し合うと、改善点もポジティブに受け止めやすくなります。
② 親の期待が負担になっていないか振り返る
「せっかくだから上手にできてほしい」「良い結果を出してほしい」という親の気持ちは自然なものですが、その期待が強くなりすぎると、子どもにとって大きなプレッシャーになります。子どもは、親の表情や言葉の端々から期待の大きさを敏感に感じ取っています。
もし本番前に子どもが極端に緊張していたり、眠れないほど不安がっていたりする場合は、「うまくやることより、今できることを出してくれればいいよ」と伝えるなど、気持ちを軽くしてあげる声かけも必要です。
「結果がどうであれ、応援している」という姿勢を、言葉と態度の両方で示していきましょう。
③ 準備や当日のサポートは、できる範囲で
衣装の準備、メイク、送り迎え、ビデオ撮影など、発表会や大会では親のやることも増えます。完璧を目指してすべてを抱え込んでしまうと、親自身が疲れ切ってしまい、「早く終わってほしいイベント」になってしまうこともあります。
できる範囲で協力しつつ、必要に応じて家族や周囲に頼ることも大切です。「写真も動画もすべて完璧に撮ろう」と頑張りすぎるのではなく、「一番見ていたい場面はしっかり目に焼き付ける」と割り切る選択もあります。
親が少し肩の力を抜いて楽しんでいる姿は、子どもにとっても安心材料になります。
発表会・大会に向き合うときの「ほどよい距離感」
発表会や大会に向けての期間は、子どもにとっても親にとっても、いつもより気持ちが揺れやすい時期です。その分、関わり方のバランスが難しく感じられることもあるでしょう。
① 子どもの本音を聞く時間をつくる
本番が近づいてきたとき、「楽しみ?」と聞くと、「うん」と答える子もいれば、「ちょっと怖い」「出たくないかも」と打ち明ける子もいます。どちらの気持ちも自然なものであり、「そんなこと言わないの」と打ち消すのではなく、まずは受け止めてあげることが大切です。
不安を言葉にできたことで、気持ちが少し軽くなることもあります。「緊張するのは、それだけ大事だと思っているからだね」といった声かけも、不安を前向きにとらえ直す手助けになります。
本音を話せる相手がいること自体が、子どもにとって大きな支えです。
② 本番後に「振り返りすぎない」選択もあり
真面目な子ほど、「ここができなかった」「もっと頑張れたはず」と、自分に厳しい振り返りをしがちです。もちろん振り返りは成長のきっかけになりますが、あまりに細かく反省しすぎると、次への足かせになる場合もあります。
本番直後は、まず「おつかれさま」の気持ちを伝え、少し時間をおいてから、「次はどんなところをがんばってみたい?」と前向きな視点で話し合うとバランスがとりやすくなります。
子どもが自分から話し出したときだけ丁寧に聞いてあげる、という距離感も一つの方法です。
まとめ:発表会や大会は「親子で成長を感じるイベント」にできる
発表会や大会は、準備も当日も大変な面がありますが、その分、子どもが大きく成長するきっかけになる場でもあります。日々の練習を続けたこと、緊張しながらもステージや会場に立ったこと、仲間と支え合ったこと──その一つひとつが、子どもにとってかけがえのない経験になります。
親としては、結果だけに目を向けず、努力のプロセスや気持ちの揺れも含めて「よくがんばったね」と受け止めてあげることが、子どもにとって何よりの励ましになります。完璧でなくていい、本番も日々の練習も含めて一つの物語だと考えれば、親自身もイベントをより穏やかな気持ちで楽しめるはずです。
発表会や大会を、子どもだけの舞台ではなく、親子で成長を感じ合える機会として、一緒に味わっていけるとよいですね。